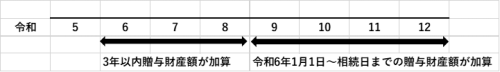新年あけましておめでとうございます。
令和6年度税制改正大綱が令和5年12月14日に自由民主党にて決定されました。
デフレ構造からの脱却で、賃上げ、民間投資の増加が今日本で動き出しています。この動きを止めることのないよう、中小企業にまで浸透するように社会を作っていくのがわが国が達成すべき政治課題です。
上記の現状認識から、
1.給与等の支給額が増加している場合の税額控除の見直し
適用期限を3年延長するが、原則税額控除等を15%から10%に引き下げる。
2.交際費等の損金不算入制度の見直し
①損金不算入となる、交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を
一人当たり5,000円から10,000円以下に引き上げる。
②接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を
3年延長する。
3.生産性向上、供給力強化に向けた国内投資の促進
①イノベーションボックス税制の創設
青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する
各事業年度において、居住者もしくは内国法人に対する特定特許権等の譲渡又は
他の者に貸し付けを行った場合に次の金額のうちいずれか少ない金額の30%に相当する金額がその事業年度の損金に算入できる。
イ.特許権譲渡取引に係る所得の金額
ロ.当期及び前期以前において生じた特許権譲渡に直接関連する研究開発費
ハ.上記ロの金額に含まれる的確研究開発費の額の合計額
等、他にも大綱案が出ています。