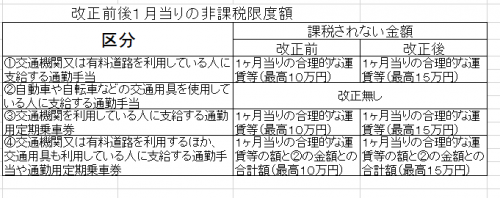平成30年分以後の所得税について、配偶者控除及び配偶者特別控除について見直しが行われます。
配偶者控除の見直し
現行の配偶者控除では、納税者本人に所得制限は設けられておらず、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入ベースで103万円以下)の場合、配偶者控除として38万円の所得控除の適用となっておりますが、見直しにより、納税者本人の段階的な所得制限が設けられることとなりました。
納税者本人の合計所得金額と控除額
①合計所得金額が900万円以下の場合、控除額は38万円(老人配偶者の場合48万円)
②合計所得金額が950万円以下の場合、控除額は26万円(老人配偶者の場合32万円)
③合計所得金額が1,000万円以下の場合、控除額が13万円(老人配偶者の場合16万円)
④合計所得金額が1,000万円超の場合、適用はありません。
配偶者特別控除の見直し
現行の配偶者特別控除では、適用対象となる配偶者の合計所得金額は、38万円超(給与収入ベース103万円超)から76万円未満(同141万円未満)でしたが、見直しにより、38万円超(同103万円超)から123万円(同201万円未満)に引き上げられることとなりました。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができない点は現行のままです。
また、現行の制度では、配偶者の合計所得金額が38万円超(給与収入ベース103万円超)、40万円未満(同105万円未満)の場合、配偶者特別控除の控除額は38万円となり、配偶者控除の控除額と同額でしたが、今回の見直しにより、納税者本人の合計所得金額が、900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が38万円超(同103万円超)、85万円以下(同150万円以下)であれば、配偶者特別控除での控除額が38万円となり、配偶者控除と同額の控除を受けることができる配偶者特別控除の枠が引き上げられることとなりました。
この見直しは、平成29年分よりの適用ではなく、平成30年分以後からの適用である為、平成29年分については、現行基準での、配偶者控除・配偶者特別控除の適用関係となりますので、ご注意ください。